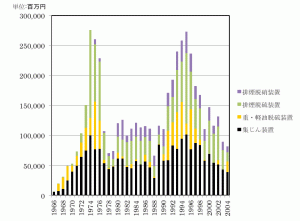高度経済成長期
脱硫・脱硝・集じん装置
イノベーションに至る経緯
我が国の大気汚染問題への取組は、愛媛県別子銅山の煙害事件に遡ることができる。1905年に操業を開始した四阪島精錬所から排出する二酸化硫黄による大気汚染に対して、住友別子鉱山(現 住友金属鉱山)は、独自に硫黄酸化物対策の技術開発を進めるとともに、1929年にドイツ人ベテルゼンの発明した塔式硫酸製造方法を導入した。当時のベテルゼン法は実験室レベルのものであったが、実用化に向けて開発を進め、世界で最初の実用化に成功した11。これにより、実害を伴う煙害は見られなくなったが、さらに、1939年には亜硫酸ガスを亜硫酸アンモニアとして回収する技術を完成させ、排煙から二酸化硫黄の排出を抑えることに成功した12。このような経験は、高度成長期以降の我が国の技術的イノベーションによる大気汚染解決の先駆けとなった。
(1) 石灰・石こう法排煙脱硫技術の開発
戦後の急速に進んだエネルギー源の転換は、石油及び石炭の占める割合を一気に総エネルギー源の90%まで押し上げた。当時、我が国が輸入する原油の85%は硫黄含有率の高い中東産原油であったことから、石油消費の拡大は硫黄酸化物による大気汚染を引き起こす可能性を有していた。1962年に「全国総合開発計画」が決定され、新産業都市建設促進法、工業整備特別地域整備促進法が公布され、大規模なコンビナート(四日市コンビナート、千葉県京葉コンビナート、岡山県水島コンビナート ※環境再生保全機構資料より)、名古屋市南部地域等、新設工業地帯が整備された。また、戦前からの工業地帯でも、既存の製鉄所等に加え、大規模な発電所が次々と建設されたため、ここでも硫黄酸化物、窒素酸化物、浮遊粒子状物質が問題となり、いわゆる「複合汚染」が大きな社会問題となった。例えば四日市市では、石油コンビナートの操業開始とともにぜんそく様の症状を訴える住民が次々と現れ、その原因究明が進む中で硫黄酸化物の影響が浮かび上がった13。
その後、公害対策基本法等が整備され、「硫黄酸化物の環境基準」が設定されると、産業界は燃料の低硫黄化、液化天然ガス等への転換、排煙脱硫装置の開発・導入に積極的に取り組んだ。低硫黄原油の輸入増大は、原油に含まれる硫黄の平均含有率を、1965年の2.04%から1969年には1.68%までに下げた。また、1967年に始まった通商産業省工業技術院(現 産業技術総合研究所)の大型工業技術研究プロジェクトでは、重油等から硫黄分を抽出するための触媒と脱硫工程に関する研究を進め、一定の成果を挙げた。1976年にはこのプロジェクトで得た知見をもとに開発された国産触媒が実用化され、直接脱硫技術は次第に国内に広まった。一方で、石油から回収された大量の硫黄が市場に供給されるようになったことから、国内の硫黄鉱山は深刻な影響を受けることになり、1973年には国内の硫黄鉱山は全て姿を消した。
東北大学工学部教授の村上は、1953年から石灰-石こう排煙脱硫技術の基礎研究を始めていた。村上は、今後の日本経済には石油が不可欠なものであるが、仮に年2億トンの原油が輸入されるとすれば、年間約400万トンの硫黄が持ち込まれることになり、硫黄酸化物による大気汚染が深刻化すると予感していた。そして、この問題を解決するためには、国内に豊富な石灰石を用いて、排ガスに含まれる硫黄酸化物を吸収・中和し、生成した亜硫酸カルシウムを空気で酸化して石こうを生産することができれば、貴重な資源としても活用できると考えていた14。村上は、ガラス製小型実験装置で始めた基礎研究により、生成された石こうが実用可能なものであることを確認した15。この成果をもとに、村上は同じ東北大学教授の堀とともに亜硫酸カルシウムを酸化して石こうを製造する方法についての特許出願を行い、特許215209号(特公昭30-2616号公報参照)として登録された。この研究には1955年に文部省から科学研究費補助金が支給され、工業化に必要な基礎データを得るための実用化研究が始められた。この試験研究は、かつて堀が勤務していた商工省(当時)東京試験所で硫安製造技術の開発に使用していた設備を用いて行われ、実用化に必要な貴重な成果を得ることができた16。そこで村上等は、1957年に保土ヶ谷化学硫酸製造装置のためのパイロットプラントによる試験を、1962年にはイソライト工業の重油燃焼トンネルキルン用装置による試験を行い、工業化のための基礎を固めた17。
1964年、村上等は日本産業技術にその特許の実施権を与えた。日本産業技術は直ちに基礎設計を行い、三菱重工業により最初の石灰-石こう法排煙脱硫装置が1965年に日本鋼管に納入された。火力発電所向けには、1972年に関西電力尼崎東発電所に納入したものを皮切りに、150基を超える装置が国内外の電力会社等に納入された18。また、米国バブコック・ウイルコック社へ技術輸出され、早い時期から海外でも注目された。国内でもバブコック日立、IHI、千代田化工機、川崎重工業等の日本のプラントメーカーが広く活用するようになり、我が国だけでなく、米国、欧州、アジア諸国等全世界の硫黄酸化物による大気汚染と酸性雨防止に寄与してきた19。
(2) アンモニア還元脱硝法触媒の開発
1970年7月に東京杉並区で運動中の女子生徒が目の刺激やのどの痛みを訴える事件が発生し、「光化学スモッグ」とその原因のひとつとされた窒素酸化物が一躍注目された。
窒素酸化物については早くからアンモニアを還元剤として注入し、窒素と水に分解することにより処理することは広く知られていた20。1975年にドイツBASF社は欧州で初めて硝酸製造プラント排ガス処理装置にアンモニア還元法を適用して稼働しており、同じ年に三菱化成工業(現 三菱化学)もこの方法を排ガス処理装置に適用して運転を開始した21。このようによく知られた方法であったことから、国内外を問わず、多くの研究者が排煙処理にこの技術を利用する研究を進めていた。しかし、重油、石炭などを燃焼するボイラー等の排煙には硫黄酸化物が含まれ、アルミナ担体上に活性成分を担持する方法で造られた触媒では硫黄酸化物とアルミナが反応して生成する硫酸アルミニウムにより触媒の活性が低下することから使用することができなかった22。このため、排煙脱硝技術の実用化には、これまでのアルミナ担体に代わる革新的触媒の開発が必要であった。
世界で最初のアンモニア接触還元法を用いた大容量排ガス脱硝装置は、住友化学工業により開発され1974年に運転を開始したメタノール改質炉の排ガス処理装置と言われている23。この技術は、その後アンモニア改質炉やボイラー排ガス処理にも適用されたが、ここで用いられた触媒は、依然としてアルミナを担体とする卑金属系触媒であった24。
日立製作所、三菱油化(現 三菱化学)とバブコック日立(以下「日立グループ」と呼ぶ)は、350℃前後の温度で高活性、高選択性を持つ触媒を開発することを目指して、試作した膨大な触媒のスクリーニングを行い、さらに、重油ボイラーの実ガスによるパイロット試験を行ったが、最初に試作した触媒はいずれもこの試験をクリアすることができなかった。そこで、改めて数千種の触媒を試作し、再びパイロット試験を実施した。この試験により、酸化チタンを担体とする触媒の耐久性が確認された。さらに、1976年から1980年にかけて電力会社の火力発電所に建設した実証プラントを用いて1~3年の試行運転を行った結果、酸化チタンが実用に十分に耐え得ることが確認された。この触媒が開発されたことにより、初めて火力発電におけるアンモニア選択接触による脱硝が実現した。
同じ頃、武田薬品工業もアンモニア選択還元法の開発を行っていた。主触媒物質を開発した後、長寿命触媒とするために種々の担体物質の探索が行われ、酸化チタンに到達した。その後、酸化チタン顔料メーカーの石原産業の協力を得て、高面積、耐熱性、耐食性のある触媒担体として酸化チタン触媒を開発し25、その特許は堺化学工業と日本ガイシに技術供与された26。
火力発電用ボイラーでは、ダストの堆積も大きな問題となり、ガス並行流形反応器が開発された。これらの技術開発により、アンモニア接触還元法による脱硝装置は、安定した自動運転が可能となり、火力発電所のボイラー、ディーゼルエンジン、ガスタービン、ごみ焼却炉等多くの分野で利用される排煙脱硝技術の主流となった27。
火力発電用ボイラー向けの本格的排煙脱硝装置の納入は、バブコック日立が1977年に関西電力海南発電所に納入したものが最初である。その後、この技術は日立製作所の重電部門の主力製品のひとつとなり28、世界市場でトップシェアを占めることになった29。このような競争的技術開発により誕生した酸化チタン系触媒技術は、国内のみならず、欧米先進国、アジア諸国にも普及し、世界の環境問題へ大きく寄与した30。
(3) 高温電気集じん・低低温電気集じんシステムの開発
電気集じん装置は、1906年に米国で開発されたもので、コロナ放電によりマイナスに帯電したばいじんがプラス極の集じん電極に付着する原理を利用して排ガス中のばいじんを除去する。我が国では1950年代にその基礎研究が行われ、1965年に初めて実機として採用された。当時主流となりつつあった石油焚火力発電所については、様々なダストが排出される石炭火力とは異なり、集じん装置を設けることは不要とも考えられていた。しかし、1968年の大気汚染防止法により規制が強化されたことから、その導入が進められ、特に大量処理を必要とする火力発電、製鉄、金属精錬、セメント等では高い集じん能力を持つ電気集じん装置の導入が不可欠となった。電気集じん装置の集じん性能はばいじんの電気抵抗に依存するが、重油燃焼によるダストは電気抵抗率が低いいわゆる「低抵抗ダスト」であったため、捕集した粒子が再び飛散する再飛散現象のために集じん率が低下するという問題を抱えていた。この問題は、低温腐食を防止するために注入するアニモニアにより硫安が副生し、電気抵抗率を上げることで対応された。
その後、二度にわたる石油危機の経験から、国際エネルギー機構(IEA)は新しく立地する火力発電所を全て石炭焚きとするという方針を採用し、我が国も石炭火力発電に再転換することになった。石炭燃焼により生じるフライアッシュ(石炭灰)は、重油燃焼ダストとは逆に電気抵抗の高いいわゆる「高抵抗ダスト」であることから、蓄積した荷電がある限界を超えると集じん極より粒子を放出する逆電離が起こり、集じん率が低下するという問題が発生した。
この状態を回避するために、各社は操作温度とダストの電気抵抗率の特性を分析し、電気集じん機の操作温度条件を調整する技術を開発した。1970年代に開発された「高温電気集じん機」は、操作温度を350℃程度の高温とすることにより電気抵抗を下げようとするものであったが、ガス温度の上昇に対応するため装置が大きくなることと、高温条件では放電量が多くなり、印加電圧が十分とれない等の問題が生じた31。
そこで電気集じん処理ガスの温度を約90℃まで下げることによりダストの電気抵抗率を大幅に下げ、逆電離現象を解消する「低低温電気集じんシステム」が三菱重工業、住友重機械工業等により開発・実用化された32。電気抵抗率が下がることによりダストの電気付着力が弱まり、ダストの飛散量が増加するものとなるが、電極の清浄度を向上させる連動無荷電槌打方式及び新型放電極の採用などによって、安定した性能を持つ電気集じんシステムが誕生した33。低低温電気集じんシステムは、装置のコンパクト化が図れ、かつ集じん性が大幅に向上するため、近年新設される石炭火力発電のほとんどがこの方式を採用している。
三菱重工業の低低温電気集じんシステムの初号機は、東北電力原町火力1号機に、2号機は中国電力三隅発電所1号機に採用された。原町1号機は1996年から石炭焚きの試運転に入り、1997年から営業運転を開始した。住友重機械工業の開発した低低温電気集じん装置は、1994年に電源開発竹原火力発電所で実証試験が行われ、1995年にモデル電気集じん機を使用したデータ収集を行った後、2000年12月より実用負荷運転に入った。
(4) 民間の産業公害投資の拡大と公害管理体制の整備
我が国の脱硫、脱硝、集じん技術の普及は、民間を含む積極的な公害対策関連投資により進んだ。1975 年度の公害対策関連投資額は9650 億円に達し、全設備投資額の18 %を占めていた34。大気汚染防止関連装置についても需要が急増し、1975年度の排煙脱硫装置、重油・軽油脱硫装置、排煙脱硝装置及び集じん装置の生産額は2900億円に達した(図2「大気汚染防止装置生産実績」参照)35。
我が国の大気汚染対策が効果を発揮できたのは、このような革新的技術の開発や積極的投資だけによるのではない。法令等による規制に加え、産業界の自主的な管理を進める制度や組織整備が行われ、またこれらの対策を実施するための人材の育成も行われた。これらの要素が有機的に連携することによって、初めて我が国の産業公害は解決されたものである36。