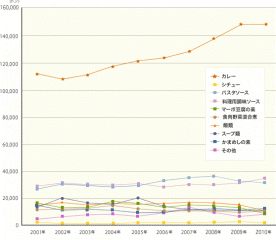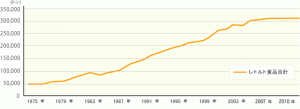高度経済成長期
レトルト食品
イノベーションに至る経緯
(1)レトルト食品開発の前史と契機
レトルト食品は、1955(昭和30)年からまず米国イリノイ大学で軍隊用食料として缶詰に代わる保存用の加工食品として研究が進められたものである。1958 (昭和33)年には、米国陸軍(NATIC)研究所とSWIFT 社との共同で、「レトルトパウチ食品」の試験的な製造が開始された。アポロ計画に代表される宇宙開発が脚光を浴びた時期と重なり、1969(昭和44)年に打ち上げられたアポロ11号にもレトルトパウチ食品が搭載される等の注目は浴びた。しかしながら、冷凍食品の普及が進んでいた当時のアメリカでは、消費者ニーズに合致せず、商業ベースに乗ることはなかった3。
アポロ11号の打ち上げから数年を経た1964年(昭和39)、大塚は関西でカレー粉や即席固形カレーを製造販売していた会社に資本参加し、新たな食品開発に取り組むこととなった。開発陣の目に留まったのが、米国のパッケージ専門誌に掲載されたソーセージの真空パックに関する記事であった。この技術との出会いをきっかけに、「一人前入りで、お湯で温めるだけで食べられるカレー、誰でも失敗しないカレー」をコンセプトにレトルトカレーの開発がスタートした4。
(2)世界初の市販用レトルト食品「ボンカレー」の誕生
商品開発にあたり、目標としたのは、「常温で長期保存が可能であること」「保存料を使わないこと」であった。
しかし、上述の通り、レトルト食品のそもそもの開発のスタートは、米軍による研究開発であったことから、必要な資材からノウハウに至るまで、その取得は困難であり、必要な技術は全て自分たちで調達・開発する以外に方法がなかった。開発に不可欠な包材もレトルト釜も当時の大塚にはなく、グループ会社で所有していた点滴液の殺菌技術を応用してレトルト釜を試作し、パウチの耐熱性や強度、中身の耐熱性や殺菌条件などのテストを繰り返し行った5。これらの地道な取り組みを通じて、レトルト食品開発のキーファクターとして、「(殺菌)温度と圧力のバランス」、「包装・充塡技術」、「ラミネートパウチの検討」の3点が浮かび上がった。
殺菌温度と圧力のバランスに関しては、カレーを入れたパウチをレトルト釜に入れ、高温で殺菌処理をすると、中身が膨らみすぎて破裂してしまうという問題があったが、テストの繰り返しにより、徐々に両者のバランスの精度を高めていった。
包装・充塡技術に関しても技術的な課題があり、パウチへの充塡時に充塡ノズルからのタレが袋口に付着したり、内容物の付着やパウチに密封される空気の量の均一化が図れない等々、各種課題が明らかになってはその改善に随時取り組む作業の連続となった。自社技術では限界があった。
パウチについては、材質・性能・殺菌条件といずれもクリアする必要があった。
1967 年に大塚は、東洋自動機の食塩の自動計量包装機「TT-10」を「ボンカレー」の自動包装に応用することを着想した。東洋自動機との検討の結果、「TT-10」とは別機種で、菓子包装用に製作していた同社の「TT-4」をベースにカレー用の充塡機の開発が進められた。最終的には包装機だけでなく、充塡機を含めた開発を進め、レトルトパウチの包装・充塡に適した両者一体型のロータリー式充塡包装機「TT-4F」を完成するに至った6。
1968年に世界初の市販用レトルト食品として「ボンカレー」が発売された。
(3)消費者が認めた「ボンカレー」の誕生
前記の通り発売に至った「ボンカレー」ではあったが、この段階で使用していたレトルトパウチは、高密度ポリエチレン・ポリエステルの2層構造の透明フィルムであり、光や酸素の透過による商品劣化等、課題を抱えたままのスタートであった。賞味期限冬場3カ月、夏場2カ月といった制約の中、商圏を阪神地区に限定しての販売にとどまった。
この耐保存性を解決するためには、前記に挙げた3番目のキーファクターであるラミネート構造の改善が必要であった。当時、東洋製罐が米国企業との技術提携により開発されたアルミ箔入りの3層遮光性パウチ技術の開発に成功していた7。これはアルミ箔を用いたラミネートによる遮光性の確立、及びヒートシール性の精度向上を実現する技術であった。大塚はこれに有用性を見いだし、同社と連携して当該技術のボンカレーへの適用に取り組んだ。この共同開発が功を奏し、遮光性、ガスバリア性の高いアルミ箔を用いた、高密度ポリエチレン・アルミ箔・ポリエステルの3層構造のパウチの開発に成功した。
そして、最初のボンカレーの発売から1年後の翌1969年に当該技術を用いたパウチにより、賞味期限は3カ月から2年へと大幅に延長した「ボンカレー」が発売された。
新たに誕生したこの「ボンカレー」は、文字通りの全国展開となった。賞味期限がほぼ8倍に延びたことで、小売店からの返品リスクも大幅に低減した。当時の人気女優である松山容子をCMに起用し、彼女をモデルにしたホーローの看板を営業マンが全国に設置(約10万枚)する等、広告宣伝での思い切った展開の結果、全国での知名度は上昇し、爆発的な販売実績につながった。
「ボンカレー」の成功はレトルト食品の市場性を証明し、同業他社によるレトルトパウチ食品の開発・商品化を一気に広めることとなった。
(4)新市場の開拓とその後のレトルト食品市場の発展
パウチ構造に改良を加え、賞味期限を大幅に改善したボンカレーは大ヒット商品となったが、同社は自社開発したレトルト食品の技術を特許などで縛る方針をあえて採らなかった。発売当初より数年後には競合商品が出てきたが、自社による独占よりも、レトルト食品市場の拡大を優先したのである。現在、市場には何百種類も、様々な味と価格等、それぞれに特徴のあるレトルト食品が販売され、日本におけるレトルト食品文化は定着・浸透している。
レトルト食品の現状を概観すると、年間生産量は、30万トンを超えている。生産が最も多い品目はカレーで、その量は14万トン超と全体の約45%を占めている。それ以外には、パスタソース(約4万トン)、調味料などの料理用ソース(約3万トン)、おかゆ等のご飯類(約2万トン)があり、マーボ豆腐や丼類の素、水産物、食肉加工品等、消費者のニーズに応えるべく多岐にわたる製品が日夜開発されている8。
生産量の増加は消費量の増加の裏返しでもある。レトルト食品の国内消費は、昭和43年に登場して以来その数量を増加し続けており、現在の消費量は約35万トンと、国民1人当たり2.8kg(180g入りの袋に換算すると15袋分に相当)である。これは10年前と比べても約1.3倍増であり、家庭消費のほか、ホテル、レストラン、飲食店、喫茶店、列車食堂などの外食産業向けや、学校、工場、病院などの集団給食用等、多様な場面でそのニーズに応えている9。
一方、世界に目を向けると、食文化の違いなどにより、欧米とアジアとでは、その普及には異なる傾向があることが見て取れる。
欧米諸国では、オーブン等での加熱調理等が食事作りの基本といった食文化の点、かつ、大型の冷凍冷蔵庫の普及等による常温保存の必要性の低さ、といった点から、レトルト食品の普及はあまり進まなかったが、それに対して、日本も含めたアジアでは広く普及している。湯を使う(ゆでる、蒸すなど)調理法が一般的で、このことが湯で温めて食べるレトルトパウチ食品のアジアでの普及につながったものと思われる。
流通量の多い国は、韓国、台湾、シンガポール、タイ、マレーシア、中国で、これらの国では国内向けだけではなく、輸出向けの生産も行っており、タイからはツナやカレーなどが日本にも輸出されている。