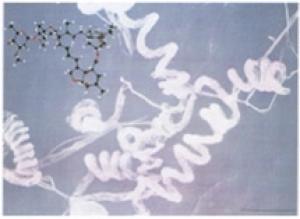安定成長期
イベルメクチン
イノベーションに至る経緯
(1)エバーメクチンの発見
1971年から1973年にかけて大村は、北里研究所から(北里大学薬学部助教授兼務)米国のコネチカット州にあるウェスレーヤン大学に留学した。留学受け入れの指導教授はメルク社の元研究所長であり、大村の留学中に米国化学会の会長にも選ばれたマックス・ティシュラーであった。留学中に大村は、このティシュラーをはじめとする米国の優れた化学者や医薬業界の有力者たちと、多くの知己を得ることになった。その中にはノーベル生理学・医学賞を受賞したハーバード大学のコンラッド・ブロック教授もいて、大村の研究の先端性に強い関心を示し1、ハーバード大学にも招聘されて共同研究をするまでになった。
留学が1年を終えるころ、北里研究所から帰国の命令が届いた。大村は、日米の研究環境の違い、とりわけ研究費の多寡のそれを痛感していた。帰国までにそれなりの研究資金の導入確保を、親元も求めていた。帰国までの短期間で大村は、コネチカット州等に存在する製薬企業等を訪問し、共同研究の提案を行った。その内容は、大村が日本において将来発見する創薬につながる微生物由来の化学物質の特許を、資金提供企業が排他的に使用する一方、研究資金の提供とその商品化による売上に対応したロイヤリティーを支払うというものであった2。この提案には大村が訪問した6つの企業や研究所が応じる意向を示した。同時に、指導教授のティシュラーは、自分の古巣のメルクにもこの提案を連絡し同社も交渉相手となった。研究資金の提示額は、メルクがけた違いに大きかった。スケールの大きい研究の必要性を追求していた大村は、メルクとの契約を優先し、帰国後正式の契約を結んだ。
大村は、大企業の研究者が既に手を付けている領域での研究ではなく、それが開発されれば大きなメリットをもたらす畜産動物の寄生虫駆除に関する薬剤の開発に取り組むこととした。そして、大村研究室の研究員たちと日々土壌中の微生物を採取し、それを培養し、そこから生成される化学物質の構造や機能を追求するための様々なスクリーニングの方法の開発、手順の組み立といった息の長い作業に取り組んでいった。このような地道な作業に必要なチームワークは、日本人に向いているとの思いがあった3。
1974年、静岡県川奈のゴルフ場周辺で大村が採取した土壌から興味深い新種の放線菌が発見された。分析の結果は、多くの作用を示す物質を生成し、それらは大村たちが求めてきた物質の可能性が高かった。大村は、その分析結果をメルク社に送り、同社で担当していたウイリアム・キャンベルがこれをもとに動物実験を開始した。寄生虫を持つマウスに微生物の培養液を飲ませると、寄生虫がみるみる減少していった。マウスから牛など多くの動物に実験の範囲を広げた結果も全て顕著な効果を示した。この微生物(放線菌:Streptomyces avermitilis 現在の学名:Streptomyces avermectinius )から、見いだされた寄生虫に有効な化合物(16員環マクロライド化合物)は、エバーメクチン(Avermectin)と命名された4。
エバーメクチンは哺乳動物への効果を更に高めるため、有機合成などの手法を用いて改良がかさねられた。そして、薬剤としてのイベルメクチンが誕生した。メルク社は、更に人体への投与に挑戦し、臨床試験を重ねて安全性を確認し、医薬製剤として完成させた。製品は「メクチザン」と名付けられ、1981年から販売された。
イベルメクチンは、寄生虫駆除や、これによる感染症に劇的な効果を挙げた。アフリカの熱帯地域に広くみられるオンコセルカ症は、アフリカの熱帯地域では多くの失明者を招く深刻な病気であった。これはブユという小さな虫が仲介してミクロフィラリアという寄生虫が体内に入り発症するものであったので、WHOでは長年にわたって仲介するブユの駆除を行ってきた。しかし、成果は上がらず、「顧みられない熱帯病」として打つ手がない状況になっていた。1988年から北里研究所とメルクは、アフリカへの無償提供を開始し、集落ごとに集団で年1回、毎年服用する制圧プログラムを展開した。この結果は劇的であった。WHOは2002年までに60万人が失明から救われ、4000万人が感染を免れ、その間に生まれた新生児1800万人が感染の脅威から救われるとともに、失明などによる労働力の低下を防ぎ、感染及びハイリスク地域の縮小や耕作可能地域の拡大などから、彼らの食糧確保が可能となったと宣言している5。
イベルメクチンの効果は、また熱帯地域83カ国、1億2000万人の患者がいるといわれるリンパ性浮腫と象皮症を主徴とするリンパ系フィラリア症などにも優れた効果があることが分かってきている。
2015年のノーベル生理学・医学賞は大村とキャンベルそしてマラリアの感染症死亡率を著しく減少させた中国の屠 呦呦博士に授与された。この功績をノーベル財団はプレスリリースで次のように示している6。
These two discoveries have provided humankind with powerful new means to combat these debilitating diseases that affect hundreds of millions of people annually. The consequences in terms of improved human health and reduced suffering are immeasurable.
(2)産学連携の推進
大村研究室がエバーメクチンの研究を積み重ねていた1975年当時、北里研究所は深刻な財政危機に見舞われていた。この年、大村は北里研究所の理事会方針として大村研究室の閉鎖を通告された。大村は教授として大学にも研究室を与えられていたので、研究所のほうのそれを整理せよとのことであった。これに対して大村は、博士号取得後の研究者やスタッフの人件費、研究経費は全て外部資金で賄うこと、外部からの導入研究費の12%を北里研究所への一般経費として研究所に支払うとの条件を示し、実質的な独立採算制での研究室運営を提案し認められた7。当時、大村の研究室が生み出す成果には日本国内でも多くの製薬会社、化学会社、飲料会社などが注目し、年間の共同研究費として支払われる金額は8000万円にも上っていた。大村研究室は優れたスクリーニングの方法を次々と開発し、エバーメクチン以外にも多くの新物質を見いだして特許化していたのである。
この研究室閉鎖案件を契機に大村は研究室の経営、更には大学や研究所の経営に深く思いをいたすようになった。研究室は成果を挙げなければ資金も供給されない。優れた成果を挙げるのは人材であり、その育成が大きな目標となった。
1981年4月から大村は北里研究所の監事、1984年5月には理事・副所長になった。監事の任命を受けて、大村は経営に関する知識を積極的に吸収し財務諸表も読みこなすまでになった。そして、北里研究所の将来性に警鐘を鳴らし、再建には新しい病院の設立という事業に取り組むことが必要との上申書を提出した。さらに、理事になってからは教授職を辞して経営に正面から取り組み、大学と研究所の相乗的発展を目指して既存の病院経営の改革、画期的な新病院の建設、看護学校、生物製剤研究所の設立といった矢継ぎ早の提案を行っていった。
こうした新規事業に不可欠な資金の確保にあたっては大村がメルク社などから受ける特許使用料収入が大きな役割を果たした。
イベルメクチンは、アフリカでは無償で提供されたが、畜産動物や犬の寄生虫としてその寿命を縮めてきたフィラリアの駆除薬として世界的に普及し、また、先進国においては疥癬病などの症例にも優れた効果を発揮してきた。これによるメルク社の得る利益は巨額なものとなった。エバーメクチンが開発された当初、メルク社は大村のもつ特許権を一時金で買い取る交渉を持ち掛けたが、大村はロイヤルティーとしての支払いを望みそれを実現していた。この結果、毎年10億円を超す収入がもたらされるようになっていた。大村はこの収入の大半を上記の研究所の強化に充当し、それを実現させていった8。第2病院となった埼玉県北本市の病院9建設には、自ら大蔵省との折衝、地元医師会との調整に奔走した。
そして、1989年、研究所所長となってからも自らの研究室をもつとともに研究所と大学との統合を提案し、その一体的な運用による人材育成、研究開発の推進を主唱した。2008年、両法人は、所要の手続きを経て学校法人北里研究所として統合し、新たなスタートを切った。
研究費の確保のため知的財産権を最も有効な方式で活用し、その収入を更なる研究、人材育成の資金に充当するという産学連携の見事な実例がここにある。