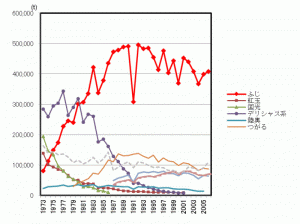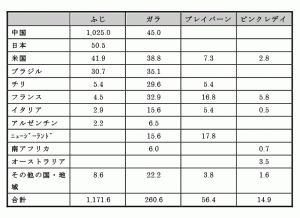高度経済成長期
リンゴ「ふじ」
イノベーションに至る経緯
我が国におけるリンゴの本格的栽培は、北海道開拓使次官であった黒田清隆が1871年に米国から持ち込んだ75品種の苗木に始まるといわれる。苗木は1874年以降、内務省勧業寮試験場から全国に配布され、試験栽培が行われた。これにより青森県や長野県等、現在のリンゴ生産地の多くが誕生した。
リンゴ生産地は寒冷地域が多いため、冷害の被害を受けることも少なくない。特に東北地方は1930年代に連続して冷害に襲われ、深刻な社会的問題ともなった。このような状況の下で東北地方の園芸振興が検討され、激しい誘致合戦の末、1938年3月に青森県南津軽郡藤崎町に農林省園芸試験場東北支場が設置された。初代支場長として藤崎に赴任した新津宏は、その研究課題を「果樹と野菜の育種」、中でもリンゴの育種を最重要課題とした3。当時、我が国のリンゴ品種の主流は「国光」と「紅玉」で、二つの品種の占有率は80%にも達していた。また「印度」を除くほとんどの品種が、明治以降に米国から導入されたものであり、消費者の嗜好性を十分に満たすものではなかった。このため、東北支場の第1次品種育成試験の最重点目標は、「日本の環境条件に適合した品種の育成」となった4。
一般に、果実の育種は、①おしべから採った花粉を別の品種のめしべにつける「交配」5、②交配でできた果実から採った「種子」を植えつけ、実生(みしょう:種から出てきた小さな木)を育て、③実生になった果実を味、形状、色、貯蔵力、木の性質、病害虫に対する強さ、栽培の容易性など様々な観点から審査して優れたものを候補として選ぶ「選抜」、④選抜されたものについて、何年も試験栽培して確認し、⑤最後に「名前」をつけ、「品種登録」するという手順で行われる。この開発には気が遠くなるような作業時間と、根気のある作業の繰り返しが求められる。
東北支場における交配は、開場の翌年から始められ、3年間の交配により4656個体の実生を得ることができた。しかし、交配実生を本圃に定植する頃から戦争の影響が強くなり、研究者が次々と召集されたことから、育種は事実上停止されることとなった。「ふじ」の誕生までには数度にわたる危機があったが、これがその最初のものであった。戦争が激しくなると、主穀類増産の掛け声が高まり、果樹は不要・不急のものと白眼視されることさえあった。このような中で、召集された研究者に代わって新たに着任した僅かな職員の懸命な努力と、外部の一部理解のある人々の激励により、交配実生が完全に守り抜かれたことは奇跡的でもあった6。
戦争が終わり、召集されていた研究者が復員し、新たな研究者も採用されて、中断していた育種も再開された。1947年には定植された実生が結実を始め、結実数を増してきた交配実生について「選抜」の基礎となる果実調査が始められた。
「選抜」は、第1研究室長であった定盛昌助が陣頭指揮した。実生の中から果実の形や色、味など優秀なものを選抜し、さらに栽培方法の簡易さ、病害虫への抵抗力、貯蔵性などの面から調査が行われた。しかしその選抜においては、国光を超えるという目標形質を備えた個体がなかなか得られず、育種担当者の間には焦燥感、悲壮感が充満した時期もあったといわれている7、8。
1949年に東北支場長として森英男が着任した。この頃には東北支場を青森県藤崎町から盛岡市へ移転することが決まっており9、その準備も進められていた。その後、この移転は無期延期となったが、この移転が行われていれば「ふじ」は生まれなかったかもしれないといわれている10。実際、支場での試験推進のための圃場の拡充整備が行われる中で、「ふじ」を生んだと同じ交配組合せの交配実生約200個体も伐採されたが、この際も「ふじ」となる個体は伐採を免れることができた。実生個体の選抜は続けられる中、1950年4月に園芸試験場東北支場は東北農業試験場園芸部と改称された。
1955年秋、育種担当者は、圃場に植えられた実生の中から一つの個体が品質及び貯蔵性において極めて優れていることを確信し、園芸部長の森英男に試食を求めた。森英男はその優秀性に着目し、担当者にこの個体に特別の注意を払って検討するよう指示した。育種担当者がこぞって「有望」と確信できた瞬間は歴史的・劇的なものであったが、この個体は、いかにも青く、商品性が危ぶまれ、また着色が優れた年と不良の年があるという不安定なものでもあった。このため、引き続き着色及び貯蔵性についての検討が行われ11、ようやく1958年の園芸学会春季大会の場で「東北7号」として発表された。
発表直後、その穂木(挿し木・接ぎ木に使う枝)が国立試験研究機関による系統適応性検定試験のために、北海道農業試験場、青森県りんご試験場、岩手県園芸試験場、山形県農業試験場置賜分場、秋田県果樹試験場、宮城県農業試験場、福島県園芸試験場、長野県園芸試験場、長野県農業試験場下伊那分場、栃木県農業試験場(試験場名は当時の名称)に頒布された。
園芸部長の森英男はまた、青森県、岩手県、長野県の精農家(リンゴ栽培を研究し、先駆的な成果を挙げている生産者)にその穂木を渡し、試作を依頼した。この中には後に「ふじの育ての親」といわれる青森県の斉藤昌美や対馬竹五郎が含まれていた。
「ふじ」の誕生を待っていたかのように、東北農業試験場園芸部の盛岡市への移転が1961年に始まった。研究者の何人かがこの移転とともに試験場を去った。最後に「ふじ」の原木が盛岡へ運ばれ、移植された。
園芸部長の森英男は、リンゴ不況の打開のためには「国光」に代わるべき品種が必要であると認識し、その普及を図るためには、農林省職務育成品種登録規定に基づく「東北7号」の命名登録(農林登録)が必要と考えた。1962年4月「東北7号」は「ふじ」と命名され、「リンゴ農林1号」として農林認定品種(旧:命名登録品種)に登録された。「ふじ」と命名された経緯について、次のように紹介されている12。
「農林省の職務育成品種の登録では、職育成品種審査会の議を経た後、農林大臣に審査結果が答申され、これを受けて大臣が命名して登録することになっている。したがって、育成者段階では最も適当と考えられる品種候補名をあげて審査会の審議にゆだねることになる。審査会においては特性について詳細な検討がなされ当時は普及の可能性についても審議された。候補名の選定段階では研究室内の議論が沸騰したが、最終的には第一候補名として全員一致で石塚昭吾技官の提案した「ふじ」とすることに決した。これには『日本で生れた世界一級の品種、日本を代表する秀峰富士のすそ野の広さにあやかり広く普及して欲しい』との希望や、『人情細やかな津軽の里『藤崎』で生れ育ったもの。その町名の一字をもらっては』との意見、さらには『絶世の美人山本富士子さんにあやかっては』とその思いはいろいろだが、「ふじ」という名称に反対するものはなかった。」
翌年(1963年)、GATT加盟によるバナナの輸入自由化が始まる。バナナの輸入拡大は、紅玉を中心としてこれまで主流であったリンゴ価格を暴落させた。さらに、1968年にはみかんや苺が大豊作となり、高度成長によりグルメ嗜好が強まっていた消費者のリンゴ離れが始まった。リンゴ価格の大暴落により特に大きな影響を受けたのが、それまで主流であった「国光」「紅玉」で、生産者が売れないリンゴを山や川に投棄するいわゆる「山川市場」が出現した13 。この結果、リンゴ生産者の収益はそれまでの4分の1にまで減少し(表1「品種更新期の青森県のリンゴ生産者の収益性」参照)、リンゴ産業も大きな転機を迎えた。
「ふじ」の市場へのデビューは、早くから穂木を渡され、試作を行っていた斉藤昌美等の生産したものにより1962年春に行われた14、15。地域の指導者、生産者団体等の中には、農林認定品種として登録されてから数年しか経っていないことや、価格が国光の倍もすることなどから、「ふじ」への転換を躊躇するものも少なくなかった。特に、我が国のリンゴ生産量の6割近く16を生産している青森県では、「国光」「紅玉」から「ふじ」への転換が大きく遅れた。その理由の一つとされたのが、「明らかに色付きがよくない」ことであった17。リンゴの色付けについて国光で成功した経験を持っていた斉藤昌美は、この技術を応用することにより、見事に着色した「ふじ」の開発に成功した。着色した「ふじ」は市場で高値を呼び、一気に人々を「ふじ」へ駆り立てることとなった18。斉藤昌美の栽培方法について、園芸部長の森英男は「特別の袋掛けを工夫して、着色を改善したことが高値を呼ぶ力となったとする考え方には絶対に賛成できない。この袋掛けは食味を落とすことが明らかであるにも拘わらず、味のよい無装果が、外観が劣るだけのことで不当に叩かれることになった」と異論を唱えた19。この確執はその後も続いたが、新品種が市場で成功する(イノベーション)際に、しばしば発生する論争とされている20。
着色したリンゴの市場での成功は、生産者を「ふじ」への移行を促すものとなった。「ふじ」の生産量は瞬く間に「国光」及び「紅玉」を凌駕した。1980年代に入ると「デリシャス系」市場が生産過剰のために低迷したことから、生産者の「デリシャス系」から「ふじ」への転換が始まり、「ふじ」の生産量は一気に「デリシャス系」を上回るものとなった(図3参照)。この差はその後も拡大を続け、1999年には全リンゴ生産量の5割を「ふじ」が占めるものとなった。品種更新が進むととともにリンゴ生産者の収益性も大きく改善された(前掲表1参照)ことから、「ふじがあって助かった」というのは生産者だけでなく、我が国リンゴ産業全体の本音でもあった21 。こうして、「ふじ」は名実ともに日本を代表するリンゴとなった。(図3「我が国の品種別りんご出荷量の推移」及び後掲統計表3「リンゴの品種別出荷量」参照)
リンゴ「ふじ」は、台湾をはじめとする海外へも輸出され、高い評価を受けた。台湾での日本産リンゴに対する需要は、戦後の輸出量がピーク時における主力商品であった「国光」「紅玉」といった低価格・小玉のものから「世界一」「陸奥」「ふじ」といった高価格・大玉品種へと変化していったが、この背景には台湾での所得増加に伴う果実消費の拡大と、高所得者層の拡大による高価格果実の購買可能層の存在が大きく作用しているとされている22。
海外の消費者による「ふじ」への高い評価は、現地での「ふじ」の栽培を拡大させるものとなった。特に早くからその導入に強い関心を持った中国では、農業省が1960年代から果樹園芸専門家を日本に派遣し、その栽培技術の習得を行った。1966年に中国調査団は、15本の「ふじ」の若木をはじめて中国へ持ち帰り、遼寧省果樹試験場と山東省果樹試験場で試作と繁殖を行った。遼寧省では1982年までに25万8000本に増殖されて、うち1万8000本が果実をつけた23。
このような努力の結果、中国の「ふじ」の生産量は1000万トンを超えるものとなった。このほか、米国、フランス、イタリア、ブラジル、チリ、アルゼンチン、韓国等でも生産が行われており、全世界の「ふじ」の生産量は1200万トンを超え、リンゴ全体の生産量の20%以上を占める「世界で最も多く生産されるリンゴ」となった(表2「代表的品種の各国での生産量」参照)。
リンゴは、原則として、挿し木や取り木で増やすことはできず、原木から採取した枝(穂木)をいろいろな系統の台木用品種に接ぎ木して増殖する。世界中のすべての「ふじ」は、盛岡市にある原木の枝を接木して増殖されたものである 。
「ふじ」は、日本で誕生した最初の世界的品種となった。